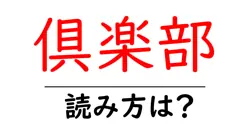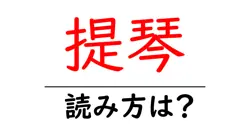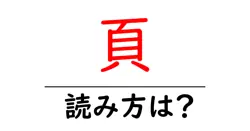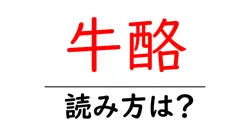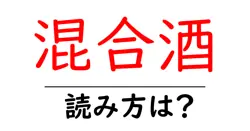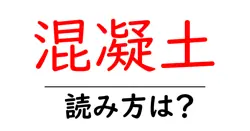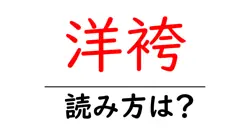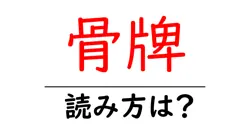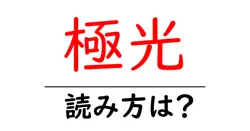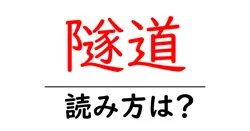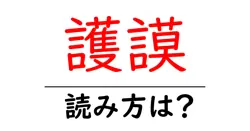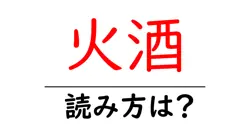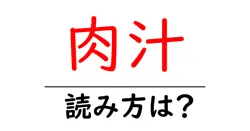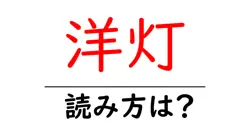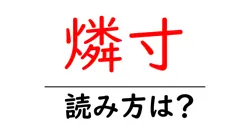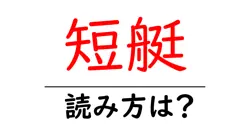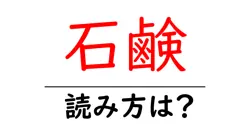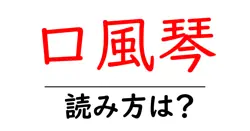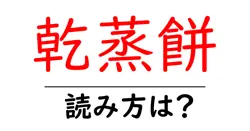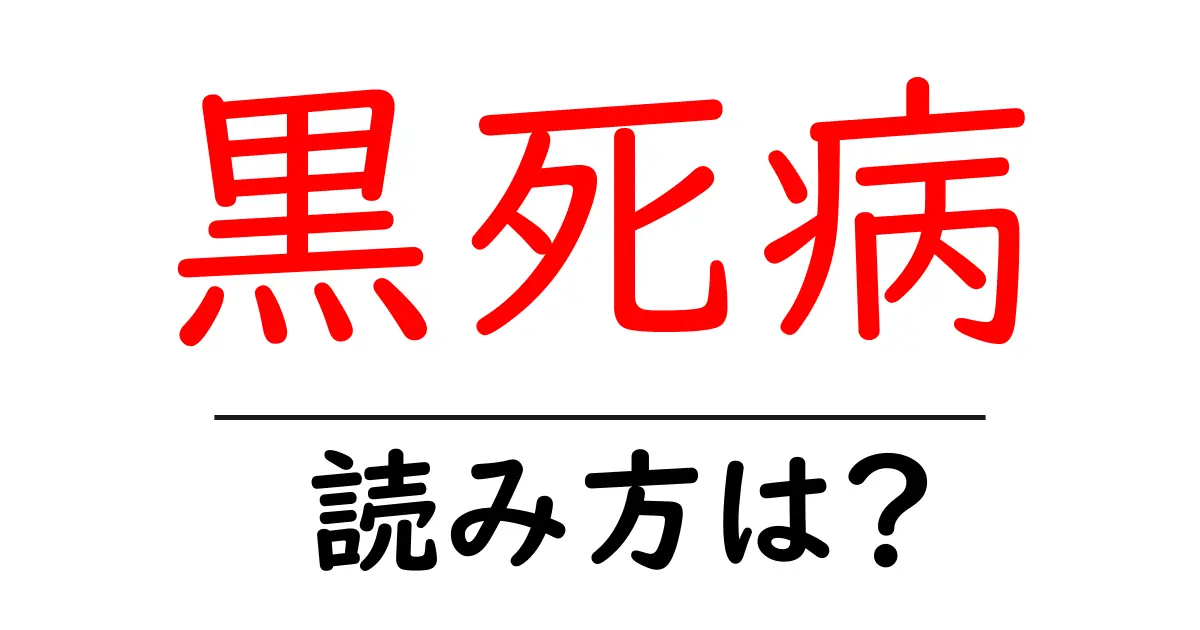
黒死病の読み方
- 黒死病

- ペスト
「黒死病(くろしびょう)」は、日本語での読み方が特徴的な言葉です。「黒死病」という言葉は、漢字の「黒」「死」「病」から成り立っています。それぞれの漢字は、音読みと訓読みがある中で、一般的には音読みが使われています。そのため、「黒」は「くろ」、「死」は「し」、「病」は「びょう」となります。この場合、全体としては音読みを用いて「くろしびょう」という読み方になります。 また、この病気を指す「ペスト」は外来語であり、フランス語の「peste」が語源です。このように、外来語が和訳されて日本語に取り入れられた際にも、異なる読み方があるため注意が必要です。言葉の成り立ちに興味を持ち、その音や意味の背景を知ることで、より深い理解が得られるでしょう。
黒死病(くろしびょう)、またはペストは、中世ヨーロッパで広がった伝染病で、黒死病という名称は、感染すると皮膚に黒い斑点が現れることからきています。この病気の原因は、ペスト桿菌という細菌で、主にノミを媒介として人間に感染します。黒死病は、14世紀に起こった大流行で特に有名であり、その結果、ヨーロッパの人口の約3分の1が亡くなったとも言われています。症状には、高熱、リンパ節の腫れ、全身の倦怠感などが含まれ、重症化すると死に至ることもあります。現在では、抗生物質などの治療法が確立されているため、早期に発見し治療することで回復する可能性がありますが、歴史においては非常に恐れられた病気でした。この病気の流行は、社会や文化、経済にも大きな影響を与え、結果的にヨーロッパの社会構造の変化を促しました。
前の記事: « 黒子の読み方は?難読語の読みと意味を解説
次の記事: 黴の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »