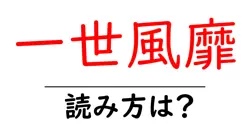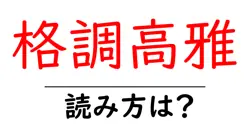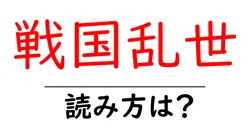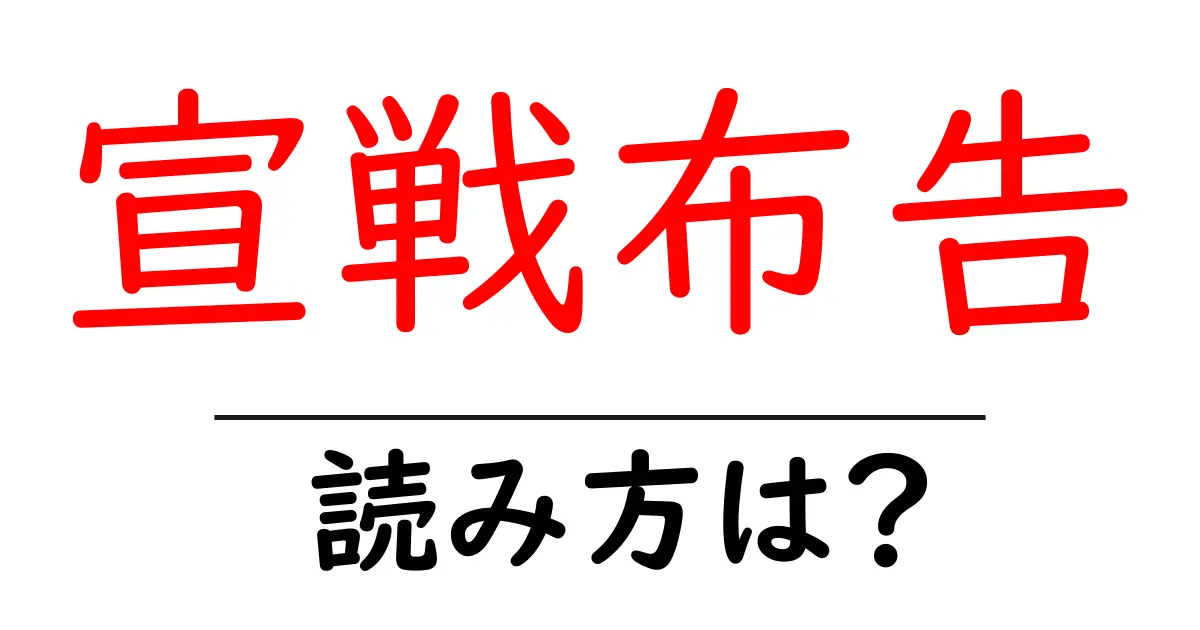
宣戦布告の読み方
- 宣戦布告

- せんせんふこく
「宣戦布告(せんせんふこく)」は日本語の四字熟語で、主に「せんせん」と「ふこく」の二つの部分に分けて考えると、その読み方に対する理解が深まります。 まず「宣戦(せんせん)」の部分ですが、ここでの「宣(せん)」は「宣言」(せんげん)などと同様に、何かを正式に言い伝えること、知らせることを意味します。そして「戦(せん)」は戦うこと、戦争を指します。したがって「宣戦」は、戦いを公式に宣言することという意味を持ちます。 次に「布告(ふこく)」ですが、「布(ふ)」は「広げる」、「告(こく)」は「告げる」という意味があり、合わせて「布告」とは広く知らせるという意味になります。このように「布告」は何らかの重要な事柄を広く世に知らせる手段として使われます。 したがって、「宣戦布告(せんせんふこく)」を分解して考えた際には、「宣戦」が「戦争を宣言する」という行為を表し、「布告」がそれを広く知らせることを示しています。言葉全体の読み方として「せんせんふこく」と覚え、意味を理解することで、文脈に応じた適切な使い方ができるようになります。
宣戦布告(せんせんふこく)とは、正式に戦争を開始することを告げる行為を指します。この言葉は、国家が敵対する相手に対して戦争を仕掛ける意志を明示的に表明することを意味します。宣戦布告は、国際法においても重要な手続きを持ち、戦争を開始する際にはあらかじめ通知を行うことが求められます。これにより、相手国に対する明確な意志表示となるため、戦争の正当性や国際社会への説明責任が生じることになります。歴史的には、若干の形式的な要素も含まれており、特に第一次世界大戦や第二次世界大戦などの大規模な戦争では、宣戦布告の内容やタイミングがが重要な意味を持ちました。
- 彼は国際問題が深刻化する中、ついに宣戦布告を行った。
- 歴史上、その国家は侵略的な行動を取る際に、ほとんどの場合宣戦布告を行った。
- 戦争宣言:戦争を開始することを公式に宣言すること。
- 宣戦布告:戦争を始めることを公に告知すること。
前の記事: « 暮色蒼然の読み方は?難読語の読みと意味を解説
次の記事: 寡聞浅学の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »