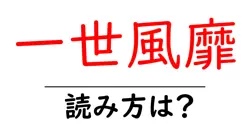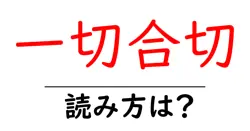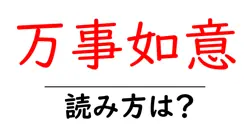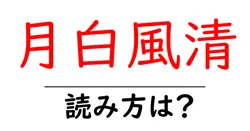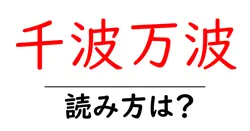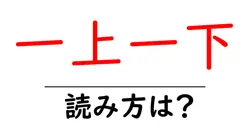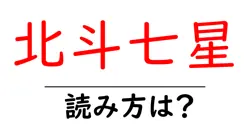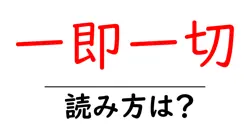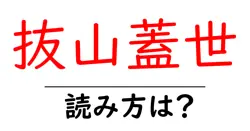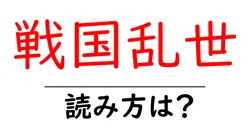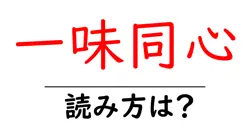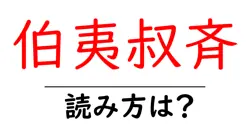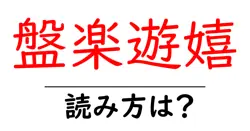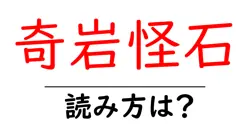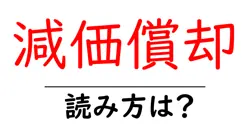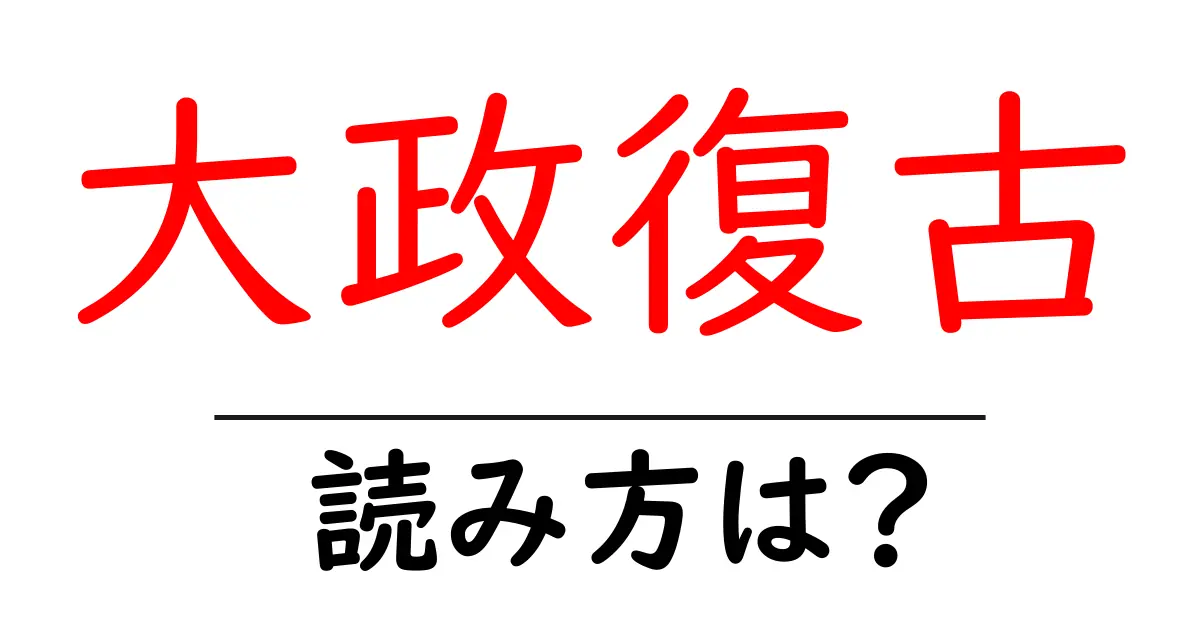
大政復古の読み方
- 大政復古

- たいせいふっこ
「大政復古(たいせいふっこ)」は、漢字の読み方を理解するのに重要な要素がいくつかあります。まず、「大」は「たい」と読みますが、ここでは「たいせい」の一部として使用されており、一般的には「おおきい」という意味も持っています。「政」は「せい」と読み、政務や政治を示す語です。 次に、「復」は「ふく」と読みます。この字は戻る、再びという意味合いを持ちますが、ここでは原点に戻ることを強調していると考えられます。最後に「古」は「こ」と読むことが多く、古いものや昔を指しますが、場合によっては「ふるい」とも読みます。 この四字熟語全体「大政復古」は、各々の漢字が意味を持ちながら結びつき、特定の意味を形成していますが、読み方としては「たいせいふっこ」と一連の音として捉えることが大切です。各音(たい、せい、ふ、こ)が連続して発音されることで一つの言葉になります。日本語の漢字の読みは、音読みと訓読みがあるため、正確な理解が重要です。
「大政復古(たいせいふっこ)」は、江戸時代末期から明治時代にかけての日本において、政治体制の大きな変革を指す言葉です。この言葉は「大政」と「復古」という二つの部分から成り立っています。「大政」とは、国家の根本的な政治に関わる事項を意味し、「復古」は古いものに戻すことを指します。したがって、「大政復古」という言葉は、古い体制や制度へと大きく政策を戻すこと、つまり、明治維新以前の天皇中心の体制への復帰を意味します。 歴史的には、1868年に行われた大政奉還の後、天皇の権力を回復し、中央集権的な新しい政治体制を構築する動きがありました。これにより、封建制度が廃され、日本は近代国家への道を歩み始めました。大政復古は日本の歴史において重要な転換点となり、多くの人々に新しい時代の希望をもたらしました。
- 明治維新において、大政復古の大号令が出された。
- この時期の大政復古は、日本の政治体制に大きな変革をもたらした。
- 政権交代:政府や政治的権力が新しい勢力に引き継がれること。
- 旧幕復古:以前の政権や体制が再び取り戻されること。
前の記事: « 大政奉還の読み方は?難読語の読みと意味を解説
次の記事: 大死一番の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »