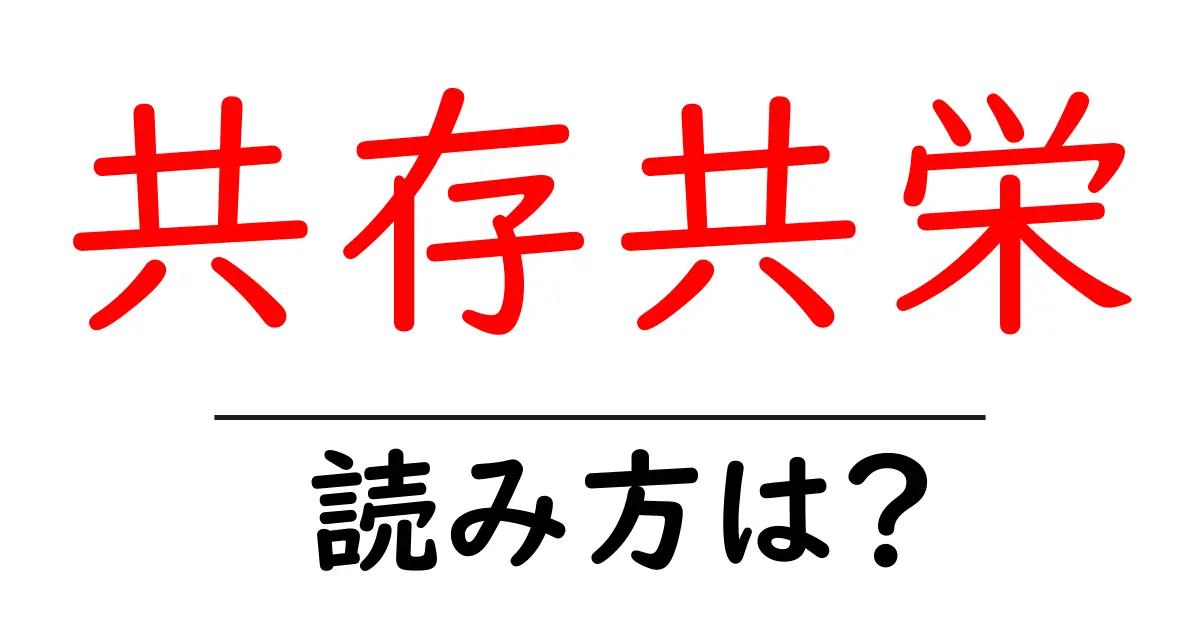
共存共栄の読み方
- 共存共栄

- きょうぞんきょうえい
「共存共栄(きょうぞんきょうえい)」は、日本語の四字熟語の一つで、それぞれの漢字に意味が込められています。この言葉は、漢字の読み方と成り立ちに注目して解説いたします。 まず、最初の「共(きょう)」ですが、この漢字は「共に」とか「一緒に」という意味を持っており、読み方は「きょう」となります。音読みであり、他の言葉と組み合わせて使われることが多いです。 次に「存(ぞん)」です。これは「存在する」という意味を持つ漢字で、音読みは「ぞん」です。この言葉は、何かがある、存在するという意味を強調する際に用いられます。 続いて「共(きょう)」が再度使われますが、前述の通り「共に」という意味があり、繰り返しで強調された形となります。 最後に「栄(えい)」ですが、この漢字は「栄える」「繁栄する」という意味があり、音読みは「えい」です。こちらも音読みとして使用され、発展的なニュアンスを持ちます。 全体を通して「共存共栄」は、音読みが多く使われる言葉ですが、響きが調和しているのもこの熟語の特徴です。また、言葉の構成からは、互いに助け合いながら共に生活し、発展していくというポジティブなイメージを与えることができます。各漢字の意味を踏まえつつ、音読みに注意を払うことが、この熟語を理解する上での大切なポイントです。
「共存共栄(きょうぞんきょうえい)」とは、異なるものや人々が共に存在し、互いに助け合いながら繁栄していくことを意味する四字熟語です。この言葉は、特に人間社会や自然界において、相互に依存し合う関係を強調しています。 「共存」という言葉は、異なる存在が一緒に成り立つことを示し、「共栄」はその中でお互いが成長し、豊かになることを表現しています。 この概念は、人種や宗教、文化が異なる人々が互いに理解し合い、支え合って生きることを促すものです。また、環境問題などの文脈でも、さまざまな生物が共に生活し、調和を保ちながら生きていく重要性を示しています。つまり、「共存共栄」は、持続可能な社会を築くための基本的な理念として、多くの場面で用いられています。
- 異なる文化が共存共栄することが求められています。
- 我々は共存共栄を目指す努力をしなければなりません。
- 協調融和:異なる者同士が協力し、調和をもって共存すること。
- 相互扶助:互いに助け合いながら共に繁栄すること。
前の記事: « 六韜三略の読み方は?難読語の読みと意味を解説
次の記事: 内憂外患の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »





















